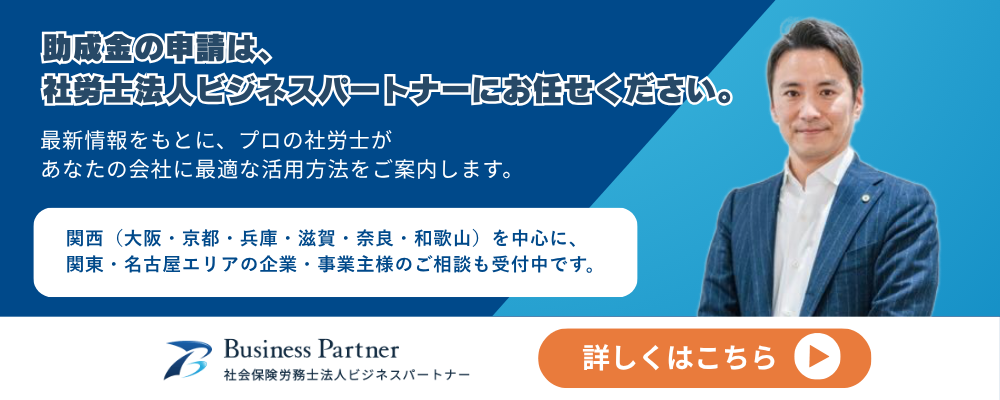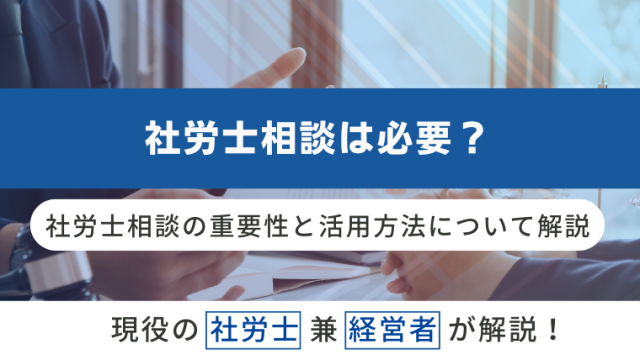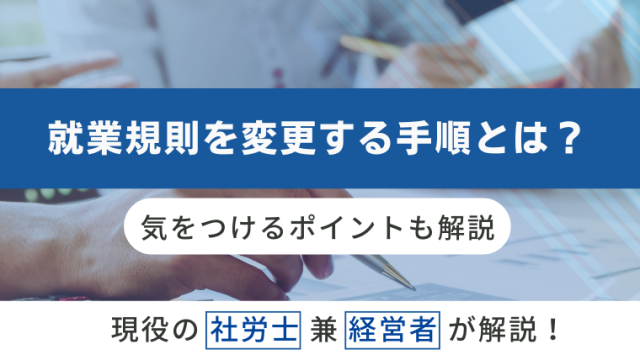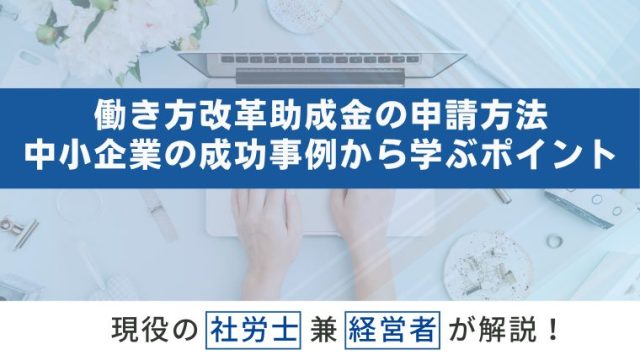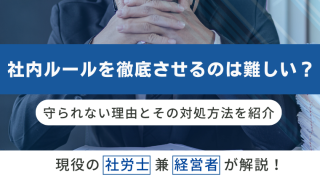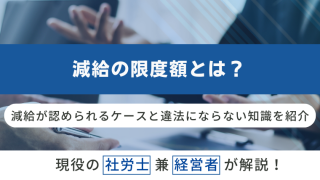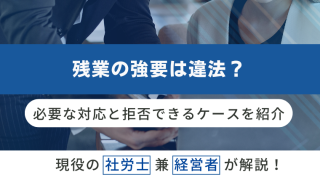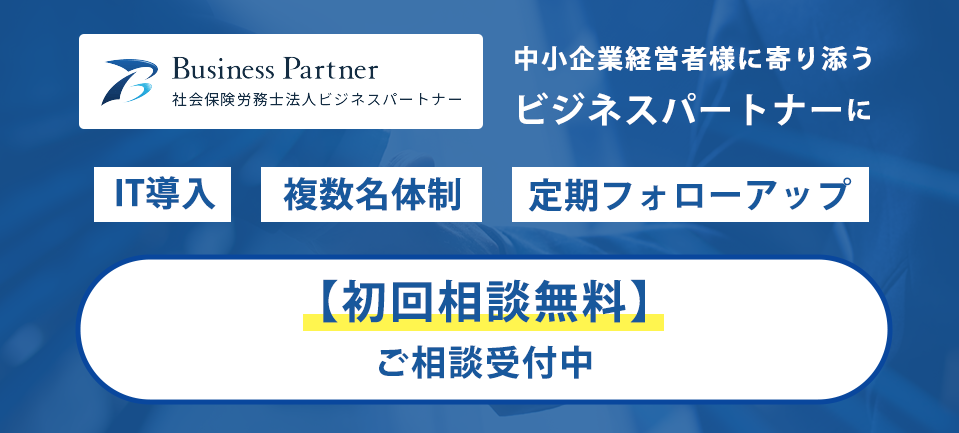経営資源の限られた中小企業にとって、「補助金」や「助成金」は事業を支える大切な資金調達手段です。しかし、「自社で使える制度がわからない」「申請が複雑で手が出せない」など以下のような疑問に悩む方も多いのではないでしょうか。
-
どの助成金・補助金が自社に当てはまるかわからない
-
申請手続きが複雑で、必要書類を整えられない
-
制度の違いや要件を誤解してしまい、チャンスを逃している
本記事では、2025年に中小企業が活用できる主要な助成金・補助金を一覧で紹介し、申請の流れや制度の選び方も丁寧に解説します。これから初めて制度活用を検討する方にも安心の内容です。
助成金・補助金の違いがわかる3つのポイント
補助金と助成金はどちらも企業の取組を支援する制度ですが、制度の性質や申請の流れ、活用メリットには明確な違いがあります。
- 補助金:経産省・中小企業庁などが実施する公募型制度。審査を経て採択された企業に支給。
- 助成金:厚生労働省所管。要件を満たせば原則受給可能な条件達成型制度。
- 助成金は労務改善や雇用維持を目的とする制度が多い。
- 補助金は「申請 → 審査 → 採択 → 事業実施 → 後払い支給」が基本。
- 助成金は「条件達成 → 書類提出 → 審査 → 支給決定」とシンプルな流れ。
- 補助金は事業計画の説得力、助成金は要件の確実な履行が重視される。
- 設備投資・人材育成・販路拡大などへの資金支援が可能。
- 経営改善や労務環境の整備を同時に進められる。
- 制度活用の実績は取引先や金融機関からの信頼向上にもつながる。
補助金と助成金は、どちらも中小企業の経営を支援する公的制度ですが、制度の成り立ちや申請方法、受給条件には明確な違いがあります。それぞれの特徴を理解しておくことで、自社にとって適切な制度選びがしやすくなり、申請の準備や判断もスムーズになります。ここでは、その違いを理解するうえで押さえておくべき3つのポイントを紹介します。
補助金と助成金の定義と違い
補助金は、経済産業省や中小企業庁などが実施する「公募型支援制度」であり、申請企業が提出する事業計画書に対する審査・選定を経て採択された場合に、上限額内で経費の一部が補填されます。競争的であるため、必ずしも申請すれば受け取れるものではありません。
一方、助成金は主に厚生労働省の所管であり、「条件達成型の制度」として設計されています。正社員化や職場環境の改善など、一定の要件を満たせば原則として受給が可能です。採択率が高く、経営改善と労務対応を並行して進めたい企業に適しています。
内容に不備があると不支給になるケースもあるため、要件の正確な把握と書類作成が重要です。
申請方法と受給までの流れ
補助金は、年度ごとの募集期間に合わせて申請が行われ、採択後に交付申請・実績報告を行い、後払いで受け取る流れが基本です。助成金も申請には資料の提出が必要ですが、要件の適合性が重視され、採択よりも「条件チェック」が中心です。
どちらも正確な情報と丁寧な準備が求められますが、補助金は事業計画の説得力が重視され、助成金は実施内容の確実性が重視される点が異なります。
中小企業にとっての活用メリット
補助金や助成金は、自己資金だけでは困難な取り組みを後押ししてくれる貴重な支援策です。たとえば設備投資や人材育成、販路開拓など、事業成長に欠かせない分野への活用が可能です。また、支援制度の活用実績は金融機関や取引先からの信頼にもつながり、経営の安定化にも好影響をもたらします。
活用すべき助成金・補助金9選【2025年最新版】
中小企業が使える助成金・補助金は多数存在しますが、それぞれ目的や対象、支給条件が異なります。ここでは2025年現在、申請可能な主要制度を厳選し、その概要と活用ポイントを紹介します。制度の比較を通じて、自社に合った支援策を検討する材料としてご活用ください。
キャリアアップ助成金
非正規雇用者の正社員化や処遇改善を行う企業に対して支給される助成金です。正社員転換、人材育成、賃金制度整備など複数のコースがあり、雇用の質を高めたい中小企業に適しています。
雇用調整助成金
経済的理由により事業活動を縮小せざるを得ない企業が、雇用を維持するための休業手当等を支給した場合に、その一部を助成します。災害や市況変動の影響を受けた際に活用されることが多い制度です。現在はコロナ特例については終了していることにもご注意ください。
働き方改革推進支援助成金
労働時間の短縮やテレワーク導入など、働きやすい職場づくりに取り組む企業が対象。労務改善や柔軟な働き方の推進を進めたい経営者に向いています。
小規模事業者持続化補助金
販路開拓や業務効率化などの取り組みに対して支援される補助金です。対象は商工会・商工会議所に所属する小規模事業者で、補助上限は最大250万円(枠により異なる)。比較的申請しやすく、初めての補助金活用に適しています。
IT導入補助金
ソフトウェアやクラウドサービスなど、業務効率化やデジタル化に資するITツールの導入費用を補助します。補助率は1/2〜2/3で、支援事業者と連携して申請します。バックオフィスの改善や売上向上を目指す企業におすすめです。
ものづくり補助金
製品・サービスの開発や生産プロセスの革新を支援。補助額は最大1,250万円で、審査項目に「革新性」や「事業性」が含まれます。製造業や技術力を活かした企業の成長戦略にマッチします。
事業再構築補助金
業態転換や新規事業への挑戦を支援。中堅・中小企業が新たな市場に進出するための設備投資や体制構築を補助します。補助上限額が大きく、思い切った再構築を行う企業にとっては心強い制度です。
省エネ補助金(エネルギー使用合理化等事業者支援)
高効率設備の導入を通じてエネルギー使用量を削減する取り組みに補助が出ます。老朽設備の更新や光熱費削減を目指す企業には費用対効果の高い制度です。
地方自治体の独自支援制度
各都道府県や市区町村が独自に実施する補助金・助成金制度も見逃せません。たとえば「設備投資支援」「創業補助」「雇用拡大支援」など、地域特性に応じた支援内容が豊富です。地元の商工会議所や自治体サイトでの情報収集が重要です。
自社に合った制度を選ぶ3つの視点
補助金や助成金の制度は多岐にわたり、目的や条件によって向き不向きがあります。中小企業が制度選びで失敗しないためには、「どの制度が使えるか」ではなく、「どの制度が自社に合っているか」という視点で判断することが重要です。ここでは、制度選定を成功させるための3つの基本視点をご紹介します。
活用目的で選ぶ(設備投資・DX・人材育成など)
まず重視すべきは、「何のために助成金・補助金を活用したいのか」という目的です。たとえば、製造設備の更新であれば「ものづくり補助金」、業務効率化やIT導入が目的なら「IT導入補助金」が適しています。雇用の安定や人材育成が課題であれば、「キャリアアップ助成金」や「働き方改革推進支援助成金」が候補に挙がります。目的と制度の趣旨が合致していることが、申請成功の第一歩です。
自社の規模・業種・条件で選ぶ
助成金・補助金にはそれぞれ対象要件があり、業種や資本金、従業員数などで制限されている場合があります。たとえば「小規模事業者持続化補助金」は従業員数20人以下(商業・サービス業なら5人以下)が対象です。申請前には必ず最新の公募要領を確認し、対象条件に合致しているかどうかをチェックしましょう。無理な申請は不採択や事務的リスクにもつながります。
地域の支援制度と組み合わせて選ぶ
見落とされがちなのが、地方自治体の独自制度の存在です。都道府県や市区町村レベルでも、設備投資・創業・雇用支援などを目的とした助成金・補助金が展開されています。これらは国の制度と併用できることもあり、事業資金を効果的に確保できる可能性があります。地元の商工会議所や自治体の支援センターを活用することで、有益な情報にたどり着きやすくなります。
申請成功に導く5つのステップ
補助金や助成金は、ただ申請するだけでは受給できません。制度ごとに求められる書類や進行フローが定められており、内容を正確に理解しておくことが、スムーズな受給と不採択リスクの回避につながります。ここでは、中小企業が助成金・補助金の申請を成功させるための5つの基本ステップを紹介します。
制度要件・公募情報の確認
最初に行うべきは、対象となる制度の公募要領をしっかり確認することです。助成金・補助金ごとに対象者や補助対象経費、提出書類、申請スケジュールが細かく決まっています。制度名だけで判断せず、内容まで読み込むことが基本です。
申請書類と事業計画の作成
次に、申請に必要な各種書類を整備します。特に補助金では、「事業の目的・内容・効果」を記した事業計画書の完成度が採択を左右します。数字やグラフ、KPIなどを用いて、誰が見ても納得できる内容に仕上げましょう。
審査通過後の実施・報告フロー
採択された後は、交付決定を受けて事業を実施し、終了後に実績報告書・経費証明書類を提出します。期日や様式の不備があると支給が遅れたり無効になる可能性もあるため、丁寧な対応が必要です。
不採択を防ぐチェックポイント
申請が通らないケースには、共通した要因があります。たとえば「計画の内容が抽象的」「予算の根拠が曖昧」「条件を満たしていない」などです。過去の採択事例や審査傾向を参考にしつつ、第三者によるレビューを受けることも有効です。
専門家に相談する3つのメリット
補助金や助成金の申請は、内容次第で採択結果が大きく左右される制度です。「制度選びに自信がない」「申請が通らなかった経験がある」などの不安を感じている中小企業にとって、専門家の力を借りることは非常に有効です。ここでは、申請前に専門家へ相談することで得られる3つの主なメリットを紹介します。
申請成功率が高まる理由
補助金や助成金は、単に書類を提出するだけで支給されるわけではありません。特に補助金の場合、提出された事業計画書の内容が審査の大きなポイントとなります。専門家に相談すれば、審査官の視点を踏まえた文書構成や数値根拠の示し方をアドバイスしてもらえるため、採択される可能性が高まります。また、誤記や要件漏れといった不備による申請無効のリスクも軽減されます。
相談できる専門家の種類(支援機関・社労士・税理士)
相談先としては、まず「認定経営革新等支援機関(認定支援機関)」が挙げられます。これらの機関には、中小企業診断士、税理士、公認会計士などが所属しており、制度選定から事業計画作成、申請支援まで一貫したサポートが可能です。
雇用に関する助成金では、社会保険労務士(社労士)が適任です。就業規則の整備や労務制度の構築といった専門的対応も求められるため、社労士との連携は大きな効果を発揮します。
また、補助金の財務部分に関しては、税理士や会計事務所の協力も重要です。数字の整合性や税務的観点からのアドバイスにより、説得力のある計画に仕上がります。
無料で利用できる相談窓口とは
「相談はしたいが、費用をかけたくない」という企業には、公的機関の無料相談窓口の利用をおすすめします。たとえば、各地の商工会議所や中小企業支援センター、よろず支援拠点では、助成金・補助金に関する制度紹介・申請方法のアドバイス・計画書のチェックなどを無償で提供しています。
これらの窓口は、制度に詳しい専門スタッフが常駐しており、客観的かつ中立的な立場でサポートを行ってくれるのが特長です。初めて補助金申請に取り組む企業でも、安心して相談できる環境が整っています。
よくある質問(FAQ)
補助金や助成金の制度は複雑で、申請を検討する段階で多くの疑問が生じます。ここでは中小企業の経営者や担当者から実際によく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。初めての申請でも安心して取り組めるよう、制度活用に関する不安を解消していきましょう。
はい、多くの助成金・補助金は個人事業主も対象としています。たとえば「小規模事業者持続化補助金」などは、一定の要件を満たしていれば法人でなくても申請が可能です。ただし、制度によっては法人に限定されるケースもあるため、公募要領を必ず確認しましょう。
制度によって異なりますが、補助金と助成金を併用できるケースはあります。ただし、同じ経費を重複して申請することはできません。制度ごとの規定に沿って、別目的での併用を計画することが大切です。
基本的には、事前に申請した内容に沿って事業を進める必要があります。ただし、やむを得ない事情がある場合は、事務局に相談のうえ「変更申請」や「中止届」を提出することが可能です。無断での変更は支給取り消しの対象になるため、必ず事前連絡を行いましょう。
その場合は、地域の商工会議所や中小企業支援センターなどの相談窓口を活用してください。事業内容や課題をヒアリングの上で、適切な制度を提案してくれるケースが多くあります。また、複数の制度を比較するために、一覧表を活用するのもおすすめです。
はい、併用できる場合もあります。ただし、補助対象経費や期間に重複があると問題になるため、申請前に両制度の要件や担当窓口に確認することが必要です。自治体の制度は国の補助金に比べて情報が見つけにくいため、地域の支援機関を通じて情報収集するのが効果的です。。
まとめ:助成金・補助金の活用は、成長戦略の第一歩
補助金や助成金は、中小企業が設備投資や人材育成、業務効率化を図る上で有効な支援制度です。本記事では、2025年に活用できる主要な制度を紹介し、制度の違いや選び方、申請の流れ、相談先まで幅広く解説しました。
重要なのは、自社の課題に合った制度を見極め、計画的に申請を進めることです。「自社にはどの制度が合うのか分からない」と感じた方は、ぜひお気軽にご相談ください。制度活用の第一歩を、私たちがしっかりとサポートいたします。