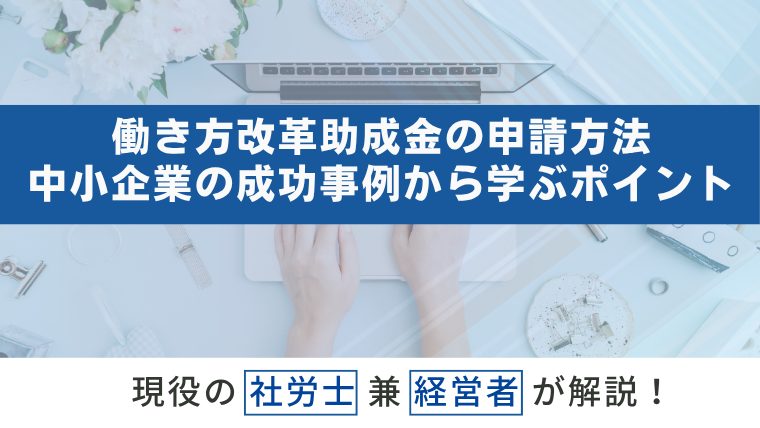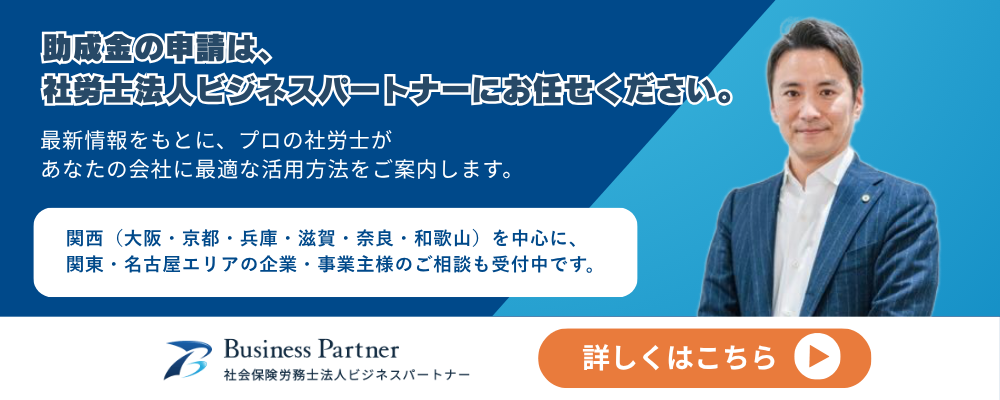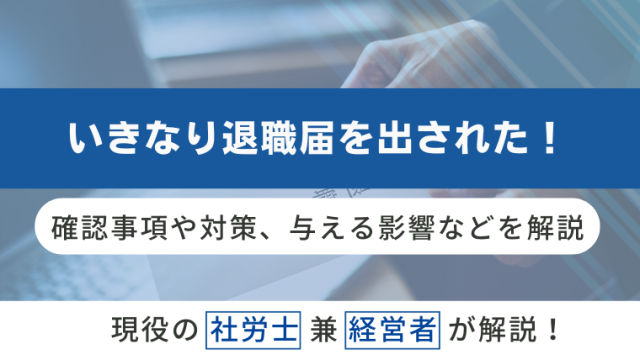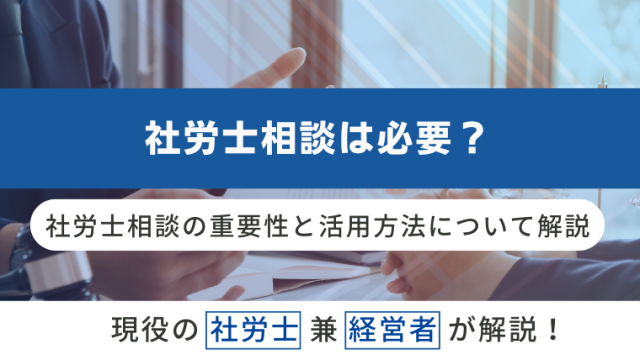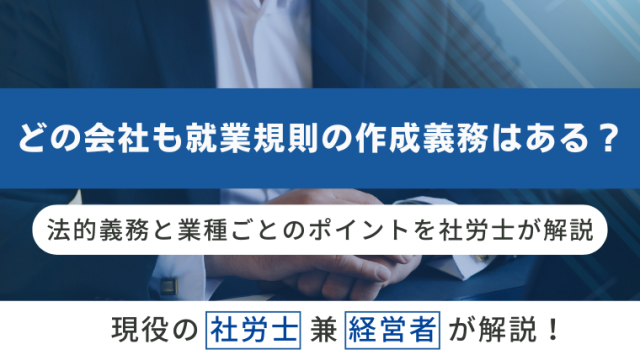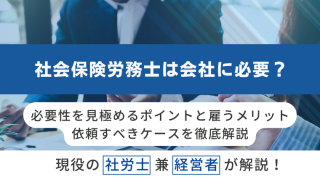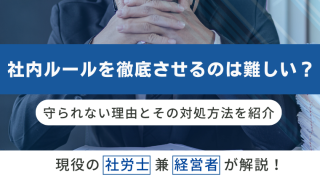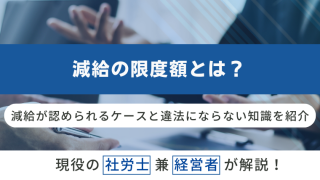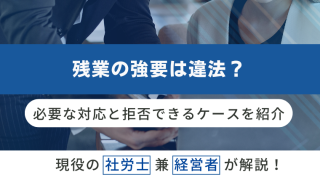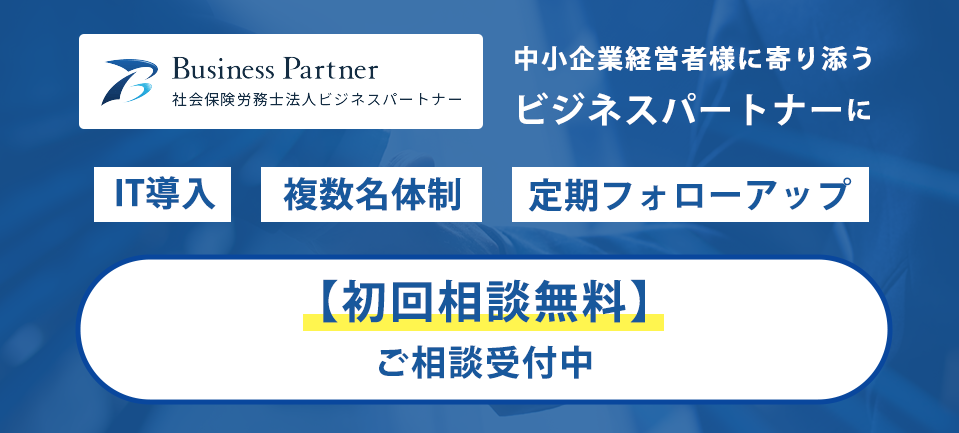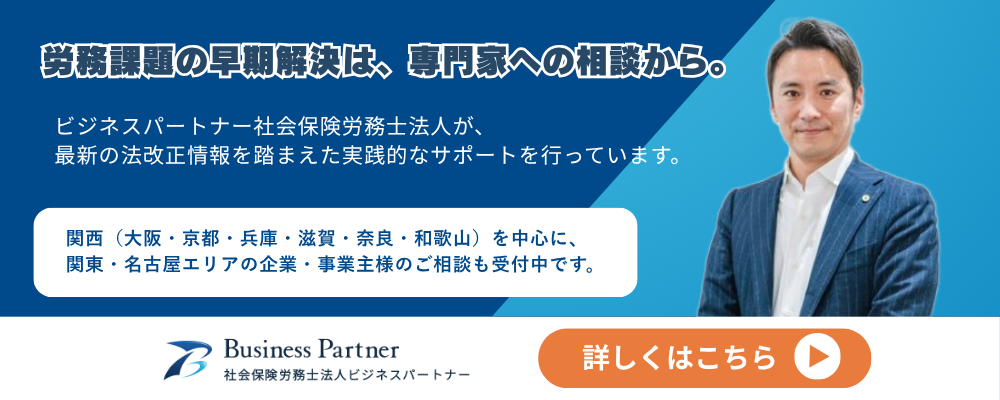働き方改革に取り組みたいけれど、コスト面や制度づくりに不安を感じていませんか?本記事では、厚生労働省の「働き方改革推進支援助成金」の申請方法と、実際に助成金を活用した企業の成功事例を紹介します。自社で使えるかどうか判断したい方はぜひ参考にしてください。
働き方改革助成金とは?制度の目的と基本情報
制度の背景にある働き方改革の流れ
日本政府は少子高齢化や長時間労働の是正を背景に、2019年から「働き方改革関連法」の段階的施行を進めてきました。これにより、労働時間の上限規制や年次有給休暇の取得義務化、同一労働同一賃金の実現といった制度改正が行われ、多くの企業に対応が求められています。こうした改革を現実的に実施するためのサポートとして創設されたのが、働き方改革推進支援助成金です。
助成金制度の概要と提供主体(厚生労働省)
この助成金は厚生労働省が提供する制度で、中小企業が働き方改革の取り組みに必要な環境整備を行う際の費用を一部補助するものです。実施内容に応じて複数のコースが用意されており、例えば「労働時間短縮」「年次有給休暇の取得促進」「勤務間インターバル制度の導入」「同一労働同一賃金への対応」などが対象になります。年度ごとに内容が見直されるため、最新情報の確認が重要です。
対象となる中小企業と支給対象経費
以下のような条件を満たす事業者が助成金の対象となります。
- 中小企業基本法に基づく中小企業であること
- 支給対象の取り組みを計画し、実施・報告まで一貫して行うこと
- 雇用保険適用事業所であること
- 過去に不正受給等がないこと
対象経費には、労務管理ソフトの導入費、研修費、就業規則改定費、コンサル費用なども含まれることがあります。
申請にあたっての前提条件と注意点
助成金の申請にあたっては、取り組みの実施「前」に計画書を提出することが原則です。取り組み後にさかのぼっての申請は認められないため、タイミングの見極めが重要になります。また、複数の助成金を併用する場合は対象経費が重複しないように注意が必要です。実施内容と助成コースの適合性が曖昧な場合は、事前に相談機関へ確認することをおすすめします。
【2025年7月版】働き方改革推進支援助成金の4つの支援コースまとめ
2025年7月版 働き方改革助成金 各コースまとめ【まとめ表】
|
コース名 |
主な目的 |
対象となる取り組み例 |
支給上限額 |
支給率 |
|
労働時間短縮・年休促進支援コース |
時間外労働の削減、年休取得率の向上 |
シフト見直し、年休計画付与、勤怠管理ツール導入 |
最大150万円 |
3/4(中小企業) |
|
勤務間インターバル導入コース |
過重労働の防止と健康確保 |
11時間以上のインターバル制度導入、社内規程の整備 |
最大120万円 |
3/4(中小企業) |
|
業種別課題対応コース |
業種特有の労務課題の解決 |
外食・運輸などの特定業種向け労務改善施策 |
最大250万円 |
3/4(中小企業) |
|
団体推進コース |
複数事業者による共同の職場環境改善 |
中小企業団体によるガイドライン策定・セミナー開催等 |
最大500万円 |
3/4(中小企業) |
※上記票の支給上限額については実施する内容等によって変動する可能性があります。
※内容は2025年7月時点の厚生労働省公式情報に基づく。出典:厚生労働省「働き方改革推進支援助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hatarakikata/
労働時間短縮・年休促進支援コース
このコースは、長時間労働の是正と年次有給休暇の取得促進に取り組む中小企業を対象としています。助成対象となるのは、就業規則の見直し、勤怠管理システムの導入、シフト制度の再構築など、労働時間や休暇取得率の改善に直結する施策です。
具体的には、36協定の範囲内で業務配分を見直す、計画的付与制度の導入、残業抑制のための社内研修の実施などが想定されています。企業規模や業種に応じて柔軟に対応できる点が特長であり、特に宿泊業・介護業などシフト制を前提とする業態でも活用しやすい制度設計です。
支給には、数値目標の設定や制度導入の成果指標の提出が求められます。制度の形骸化を防ぐため、単なる制度導入にとどまらず、運用実態まで問われる点に注意が必要です。
勤務間インターバル導入コース
勤務間インターバル制度とは、終業から次の始業までに一定時間以上の休息時間を確保する仕組みです。このコースでは、インターバル時間を11時間以上に設定し、制度として運用できるよう就業規則に明記することが求められます。
実施にあたっては、制度導入のための規則改定、社内説明会、従業員の意識啓発、勤怠システムの改修が必要です。特に注意すべきは、実際にインターバル時間が確保されていることを、勤怠記録などで証明できる体制の整備です。
この助成金は、健康経営・働きやすさ改善の取り組みとしてPR効果も高く、離職率の改善や企業イメージ向上にもつながりやすい点が評価されています。
業種別課題対応コース
本コースは、外食、運輸、建設、小売など特定業種に共通する労務課題への対応を支援する目的で設けられています。業種に特化した「働き方改革モデルプラン」に準じた対応策を取ることが助成条件です。
たとえば、外食業ではピーク時の人員体制強化とシフト柔軟化、運輸業では拘束時間の見直しやデジタコ活用、小売業では繁忙期の事前休暇取得制度導入など、実態に即した取り組みが求められます。
申請にあたっては、業種ごとの課題認識と具体的改善計画を記載した実施計画書の精度が重要となります。標準的なフォーマットは用意されていますが、実情に即した独自施策を盛り込むことで、申請審査での評価が高まる傾向にあります。
団体推進コース
団体推進コースは、商工会議所や中小企業団体が主体となり、複数の事業者の職場環境改善を横断的に支援する制度です。個社単位ではなく、地域や業界レベルでの課題解決を目的とした取り組みに対して助成が行われます。
対象となる活動には、ガイドラインやモデル就業規則の作成、合同セミナー・研修の開催、共通のITツール導入支援などが含まれます。支給額も他コースより高めに設定されており、広域での連携体制を整備することにより、より効果的な働き方改革の推進が期待されています。
申請には、構成員の名簿や取組内容の共有計画など、団体としての一体性を証明する資料の提出が求められます。行政・支援機関との連携も想定されており、社会的意義の高い取組が評価されやすい傾向です。
助成金申請の流れと必要書類
事前準備(対象施策の選定・計画書作成)
助成金の申請は、事前の準備段階が成否を大きく左右します。まずは、自社が抱える課題と助成金制度がどのようにマッチするかを見極める必要があります。そのうえで、対象となる取り組み内容を選定し、実施計画書を作成します。この計画書は助成対象経費の根拠となる資料にもなるため、導入の背景・目的・実施方法を具体的に記載することが求められます。
申請から受給までの手続きステップ
以下の流れで進行します。各ステップでの漏れがないよう、時系列で管理することが大切です。
- 計画書の提出(取組開始前)
- 取組の実施(制度導入・運用)
- 実績報告書の提出(完了後の実績を報告)
- 支給申請(経費証憑とともに申請)
- 審査・支給決定・振込
手続きには所定の様式が必要となり、計画書・報告書ともに内容の整合性が重要です。
必要書類と記入上のポイント
申請に必要な書類は複数にわたるため、あらかじめチェックリストで整理しておきましょう。
これらの書類は、制度の趣旨に照らして適切に整備されている必要があります。特に、経費証憑は支給額の審査に直結するため、内容・日付・宛先などが明確に記載されていることが重要です。
申請でよくあるミスと対策
最も多いのが、計画書を提出する前に取組を始めてしまうミスです。助成金は事前申請が原則のため、着手のタイミングには注意が必要です。
次に多いのが、実績報告と計画書の内容にズレがあるケースです。取り組み内容が計画と異なると不支給のリスクが高まるため、変更がある場合は事前に修正届を提出しましょう。
また、領収書や見積書などの証憑が不足・不備になっていることもよくあります。宛名・日付・金額が明確な書類を揃え、出費の根拠が説明できるようにしておくことが大切です。
さらに、旧年度の申請様式を使用していることも見落としがちです。提出前に厚生労働省の公式サイトで最新版を確認することで防げます。
申請成功のカギを握る3つのポイント
対象となる取組内容の具体性を高める
助成金の審査では、計画内容の具体性が重視されます。たとえば「残業を減らす」といった抽象的な表現ではなく、「〇月までに1人当たり月10時間削減」「インターバル制度を導入し、11時間の休息を確保する」といった定量的な目標を記載することで、説得力が高まります。加えて、実施方法・対象部署・活用するツールや制度の名称まで盛り込むと、採択率の向上につながります。
実施体制の明確化とスケジュール管理
助成対象となる取組を確実に実施するには、社内の体制と進行スケジュールの整理が欠かせません。以下の点を事前に固めておくと、計画実行の精度が高まります。
- 担当部署・責任者の明確化
- 関連部署との連携体制(人事・経理・現場など)
- 実施期間・報告日程・申請期限の逆算スケジュール
- 業務フローの変更点や社内周知のタイミング
社内の体制が曖昧なままだと、進行遅延や申請ミスにつながりやすくなるため注意が必要です。
費用見積もりと裏付け資料の整備
助成金は実際にかかる費用の一部を支給する仕組みのため、費用根拠の提示が求められます。以下のような資料を整えておくとスムーズです。
- 導入予定サービス・機器等の見積書
- 外部委託する場合の契約書案・作業内容明細
- ソフトウェア・研修・制度整備にかかる経費の内訳書
- 経費の支払予定日や証憑の発行時期の管理リスト
裏付け資料が弱いと、申請が否認される可能性もあるため、早期の準備が有効です。
助成金の活用事例から学ぶ成功のヒント
製造業A社:勤務間インターバル導入で残業削減に成功
A社は従業員の長時間労働が常態化していたため、「勤務間インターバル制度」の導入を決定。就業規則を見直し、退勤から翌日の出勤までに11時間以上の休息時間を設けました。制度変更に伴う社内研修やシステム改修費を助成金で賄った結果、残業時間が平均15%減少。従業員の疲労感も軽減され、離職率も改善傾向に転じました。
小売業B社:有給取得促進で定着率と満足度が向上
B社では、有給休暇の取得率が低く、従業員の不満につながっていました。そこで「年次有給休暇取得促進コース」を活用し、休暇取得推奨日やリフレッシュ休暇制度を導入。以下のような施策を実施しました。
- 年間の計画付与スケジュールを全社員に提示
- 店舗間で交代制シフトを見直し、取得しやすい体制へ
- 取得実績を定期的に人事が確認し、未取得者へ声かけ
これにより、有給取得率は前年比で20ポイント以上改善し、定着率や従業員満足度にも好影響がありました。
IT業C社:同一労働同一賃金への制度整備で助成金活用
C社は非正規社員の待遇改善を目的に、職務評価制度と賃金テーブルを導入。同一労働同一賃金の実現に向けて制度整備を進める中で、社労士の助言を受けながら就業規則と評価制度の改訂を行いました。制度策定や研修にかかった外部コンサル費用は助成対象となり、実質負担を大きく抑えることができました。結果的に社内の不公平感が減少し、正社員登用希望者の増加にもつながっています。
※本記事の事例は、実際の企業の傾向や公的資料・支援実績をもとに構成した仮想のケースです。助成金活用のイメージを具体的につかんでいただくことを目的としています。
事例から見えた共通ポイントと成功要因
紹介した企業に共通していたのは、以下のような点です。
- 明確な課題意識に基づく施策の選定
- 社内への制度導入と運用体制の整備
- 費用根拠や計画書の具体性確保
- 社労士・外部専門家の活用による精度向上
助成金を「単なる資金援助」とせず、制度改善の一環として戦略的に活用する姿勢が成功の鍵といえます。
社労士に相談するメリットと活用方法
制度変更やコース選定の相談が可能
働き方改革助成金は毎年内容が更新され、対象となるコースや支給要件が変わることがあります。制度の読み解きや該当コースの選定に不安がある場合、社労士への相談が有効です。特に、複数の助成金を併用する際や、対象経費の重複を避ける必要がある場合は、制度に精通した社労士のアドバイスが判断を助けます。相談の初期段階で方向性を固めることで、スムーズな申請準備が可能になります。
書類作成・申請のアウトソーシングでミス防止
助成金の申請には煩雑な書類作成が伴います。社労士に依頼することで、次のような作業をアウトソースすることができます。
- 実施計画書や申請様式の作成代行
- 就業規則・賃金規定などの修正提案
- 実績報告書のチェックと整合性の確保
- 証憑管理やスケジュール調整の支援
申請ミスの回避だけでなく、担当者の負担軽減や業務効率化にもつながります。
顧問契約による継続的な助成金対応
単発のスポット相談も可能ですが、複数年にわたって制度を活用したい場合は、社労士との顧問契約が有効です。定期的な法改正の情報提供や、制度変更時の対応提案など、企業の労務戦略に沿ったアドバイスが継続的に得られます。また、他の助成金制度や労務改善施策との連携提案も受けやすくなり、制度活用の幅が広がります。
無料相談を活用するタイミングとは
多くの社労士事務所では、初回の無料相談を提供しています。以下のような状況では、気軽に相談してみることをおすすめします。
- どの助成金が使えるか判断できない
- 自社の取組が助成対象になるか不明
- 書類作成に不安がある
- 過去に不支給だった経験がある
早期の相談により、制度の適合性を客観的に確認でき、無駄な準備のリスクを減らせます。
まとめ
働き方改革助成金は、制度導入や職場改善に取り組む中小企業を後押しする有効な手段です。ただし、申請には明確な計画と丁寧な準備が不可欠であり、事前の情報収集と制度理解が成功のカギとなります。実際の活用事例からも分かるように、課題に即した具体的な取組と、社内体制の整備が助成金の受給につながっています。制度の活用を検討している企業は、まずは信頼できる社労士への相談から始めてみてはいかがでしょうか。