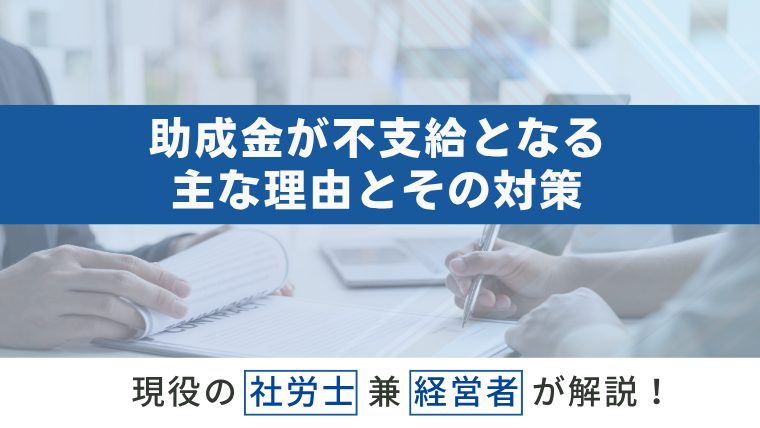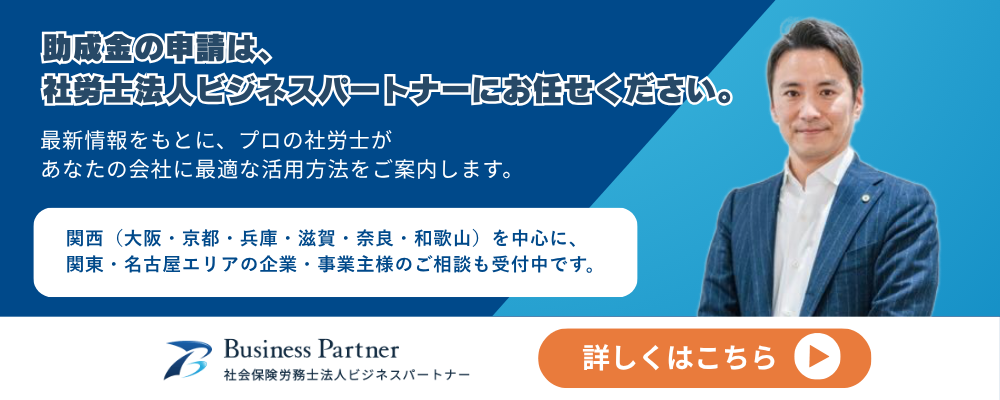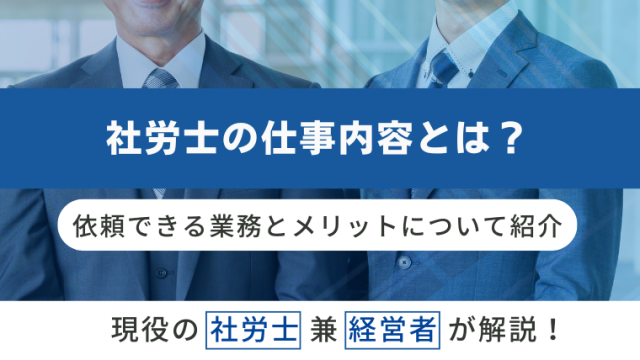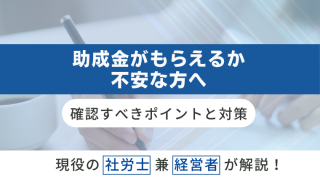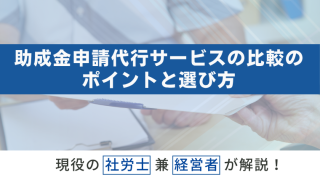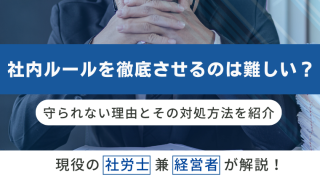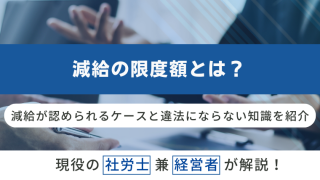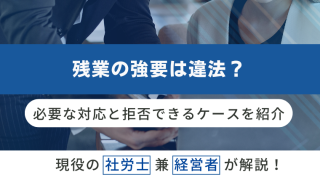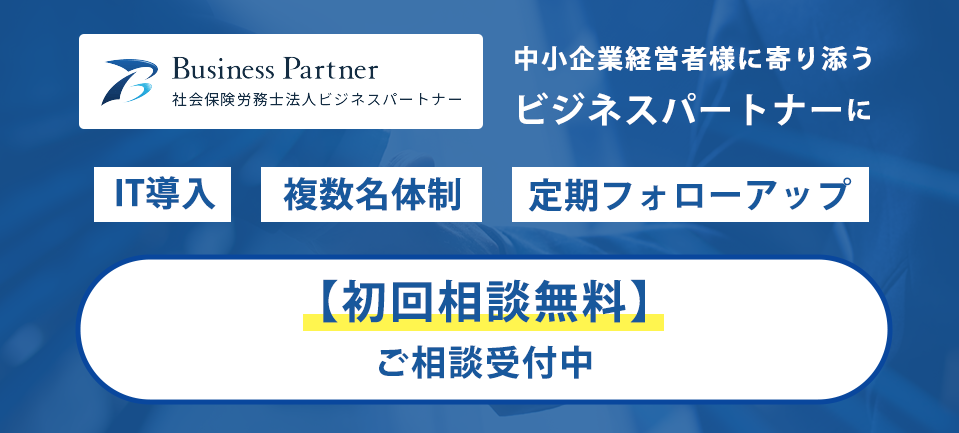「申請したのに助成金が支給されなかった…」そんな経験をした企業も多いのではないでしょうか。
-
書類は揃えたつもりなのに不支給通知が届いた
-
要件を満たしていなかったのか判断できない
-
何を改善すれば次回は支給されるのか知りたい
不支給の多くは、書類不備や要件の誤認など“基本的な見落とし”が原因です。本記事では、助成金が不支給になる主な理由を整理し、再申請や今後の申請でミスを防ぐための具体的な対策を紹介します。
助成金が不支給になる5つの主な理由

助成金の不支給は「小さな見落とし」から発生することが多く、制度要件や提出時期を誤ると支給対象外になります。ここでは、企業が特に注意すべき代表的な5つの原因を整理しました。
対象となる雇用形態・在籍期間・労働条件・事前届出の有無など、制度ごとに定められた条件を正しく把握していないケース。
「該当するはず」という思い込みによる誤申請に注意。
申請期間中に解雇や会社都合退職があると、雇用安定を目的とする制度趣旨に反すると判断される。
特にキャリアアップ助成金などは過去の解雇歴でも不支給になる場合あり。
添付漏れ、記載誤り、日付の不一致、様式の旧版使用などが典型。
書類の整合性チェックを怠ると、審査が行われず自動的に不支給となるリスク。
過去1年以内に労働基準法・最低賃金法などへの違反がある場合、支給停止の対象となる。
未払い残業・就業規則未整備・労働時間管理の不備なども該当。
実態と異なる記載や虚偽内容の申請は即時不支給。
意図的でなくても、証拠書類の不一致や説明矛盾があると「不正疑い」と判断されることも。
制度の支給要件を満たしていない
助成金制度には、支給対象となるための要件が明確に定められています。たとえば、対象となる労働者の雇用形態や在籍期間、労働条件通知書(または雇用契約書等)の有無、事前の届出が必要な場合などが該当します。
制度ごとに細かく異なるため、要件を正しく把握していないと、申請自体が認められない結果になってしまいます。制度の読み間違いや「うちも該当するはず」という思い込みは、想定外の不支給につながることがあります。
会社都合退職や解雇が発生している
助成金の多くは、雇用の安定を目的として設計されています。そのため、申請期間中に会社都合退職や解雇があると、制度の趣旨に反すると判断され、不支給の対象となるケースがあります。特にキャリアアップ助成金などでは、解雇歴があるだけで審査に通らなくなることもあるため注意が必要です。
以下のような状況が該当します。
- 正社員化した日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、従業員を整理解雇している
- 離職票上の理由が「会社都合」になっている従業員が複数いる
- 解雇理由の正当性に疑義があると判断される
支給申請と時期が重なる人員整理は、必ず専門家に相談し、影響を精査してから進めることが求められます。
申請書類の不備や提出ミスがある
助成金の申請では、必要な書類を正確にそろえ、期限内に提出することが前提となります。提出物にミスがあると、審査自体が行われずに不支給になることもあります。
たとえば、出勤簿や賃金台帳の添付漏れ、記載内容の不一致、申請日と実施日の齟齬など、ほんの小さなミスでも支給の判断に影響します。申請業務を担当する人が制度に慣れていない場合、チェック体制がない企業では見逃しやすいポイントです。
労働関係法令に違反している
企業が支給申請日の前日から過去1年間に労働関係法令(労働基準法や最低賃金法など)に違反していた場合、それが審査時に発覚すると助成金が不支給となる可能性があります。制度の健全な運用を保つ観点から、行政側も違反歴には厳しく対応しています。
違反に該当する主な例には以下があります。
- 未払い残業代がある
- 労働時間の管理が適切に行われていない
- 就業規則が未整備で労働条件が曖昧になっている
一度の違反でも、それが助成金審査の対象期間内であれば、支給は見送られることがあります。
虚偽申請・不正受給の疑いがある
虚偽の内容で申請を行った場合や、審査の過程で不正の疑いがあると判断された場合は、即座に不支給となります。
悪質なケースでは、過去の支給金返還や法的措置が取られることもあります。意図的ではなくても、書類の整合性がとれていない場合や、実態と食い違う説明が含まれていると「不正の疑い」と判断されてしまう恐れがあります。
信頼を損なわないためにも、客観的に確認可能な証拠書類と、正確な記載内容を揃えることが不可欠です。
不支給を防ぐために企業が取るべき3つの対策

制度の最新要件を事前に確認しておく
助成金制度は、年度ごとに内容や要件が見直されることが多く、昨年度は対象だった取り組みが、今年度は対象外になるケースもあります。そのため、古い情報をもとに申請準備を進めると、不支給につながる恐れがあります。以下のような対応が有効です。
- 制度ごとの公募要領や支給要綱を必ず最新版で確認する
- 厚生労働省や都道府県労働局の公式サイトで随時情報収集する
- 制度改正があった場合は、申請内容や計画書を柔軟に見直す
特に複数の助成制度を併用する場合は、重複支給が禁止されているものもあるため、制度間の整合性にも注意が必要です。
労務管理体制を整備・見直す
助成金申請においては、就業規則・賃金台帳・出勤簿・雇用契約書などの労務関連書類の整備状況が厳しくチェックされます。これらが不十分だと、要件を満たしていても不支給と判断されるリスクがあります。
- 労働時間の管理や給与計算が正確に行われているか確認する
- 労働契約書や就業規則の内容が現行の法令と合致しているか精査する
- 過去にトラブルや違反があった場合は、改善履歴を明確に示せる体制を整える
とくに、中小企業では「人事労務は担当者に任せきり」「紙管理が中心」という体制のまま申請に入ることが多く、準備段階から体制を整えることが不支給防止の鍵となります。
専門家(社労士)への相談体制を整える
助成金制度は年々複雑化しており、自社だけでの申請判断はリスクを伴います。そこで、社会保険労務士(社労士)などの専門家に相談する体制をあらかじめ構築しておくことが有効です。社労士は、制度の最新動向に精通しているだけでなく、申請書類の作成支援や内容チェック、労務体制のアドバイスも行ってくれます。特に「初めての助成金申請」や「過去に不支給を経験した企業」には、第三者視点の確認が欠かせません。社内で完結させるよりも、リスクを可視化しやすくなるという点でも大きなメリットがあります。
不支給になってしまった場合の対応方法
不支給通知の内容を正しく把握する
不支給通知が届いた場合、まずはその理由を正確に読み解くことが重要です。通知書には「申請内容が要件を満たさない」「書類の不備」「法令違反の疑い」など、具体的な不支給理由が明記されています。これをもとに、どの部分が問題とされたのかを冷静に確認しましょう。
ここでの対応が今後の再申請や別制度の活用可否にも影響するため、通知書を見落とさず、曖昧な点は管轄の窓口に問い合わせて確認することをおすすめします。
再申請・再審査請求の可能性を検討する
制度によっては、不支給後でも以下のような対応が可能な場合があります。
- 軽微な不備であれば、修正後の再申請が認められるケース
- 労働局などへの再審査請求ができる制度がある(例:キャリアアップ助成金など)
- 申請期限内であれば、別計画での申請に切り替える余地がある
ただし、虚偽申請や重大な法令違反と判断された場合は、再申請が認められないこともあります。再チャレンジを検討する際には、社労士などの専門家と一緒に不支給の原因を再評価し、計画の再構築が必要です。
他の助成制度への切り替えも視野に入れる
ひとつの制度で不支給となっても、別の助成金制度で要件を満たす可能性はあります。たとえば、雇用関連の助成金で不支給となっても、支給要件を満たしているのであれば、業務改善助成金や人材開発支援助成金など、事業内容に応じた制度に切り替えることが可能です。
制度間で対象となる取り組みや書類要件が異なるため、過去の申請経験を活かしながら、より適した制度を選定する姿勢が大切です。助成金申請は一度きりではなく、継続的な取り組みとして捉えることが、結果的に成功率を高めるポイントになります。
まとめ
助成金が不支給になる背景には、制度の要件に合致しないケースや、書類の不備、法令違反など、実務上見落としがちなポイントが多く存在します。とくに「知らなかった」「うっかりミスだった」といった小さな見逃しが、不支給という重大な結果につながることは少なくありません。
不支給を防ぐためには、制度の最新情報を常に確認し、社内の労務管理体制を整え、必要に応じて社労士など専門家の力を借りることが重要です。万が一不支給となってしまっても、通知内容を正しく理解し、再申請や他制度への切り替えといった前向きな対応を取ることで、次に活かすことができます。
助成金は事業を推進するための貴重な資金源です。制度を正しく理解し、適切な準備と運用によって、確実な受給につなげていきましょう。