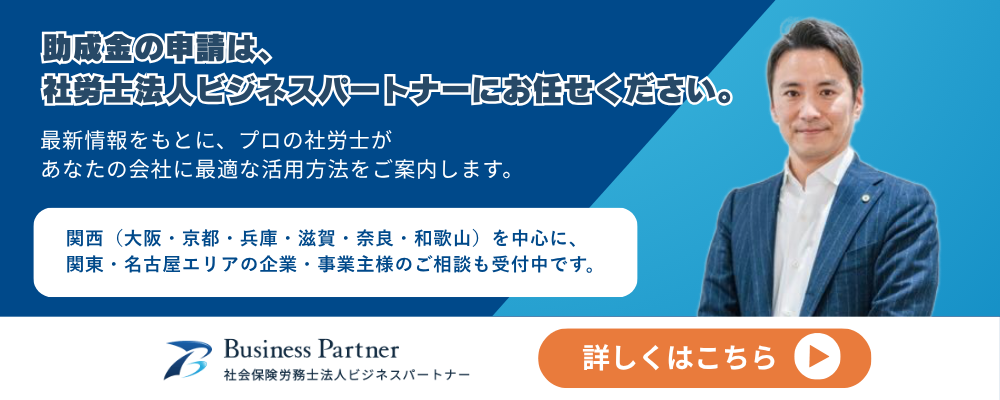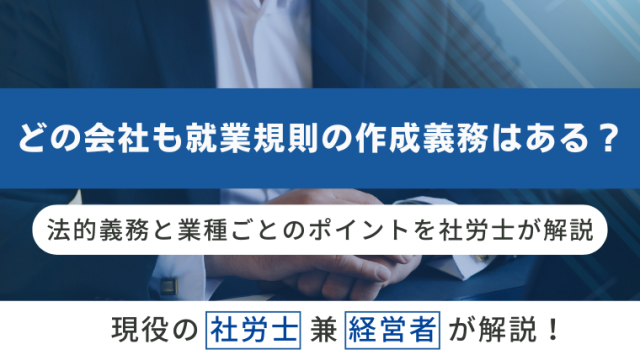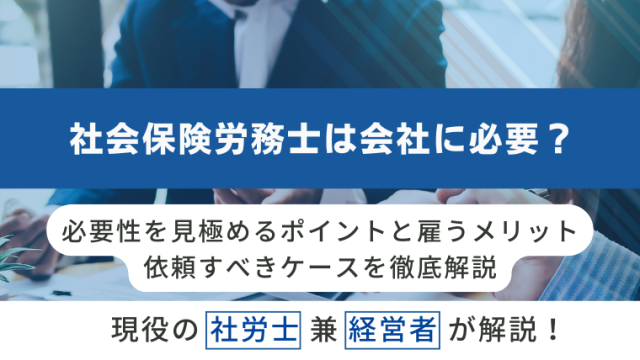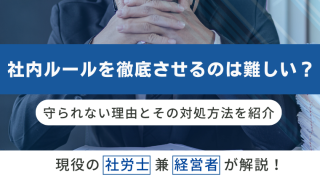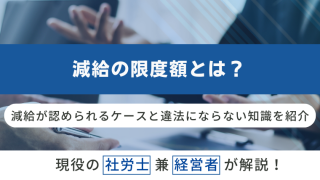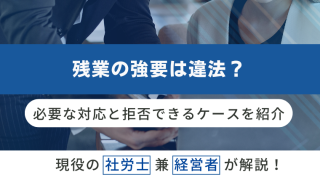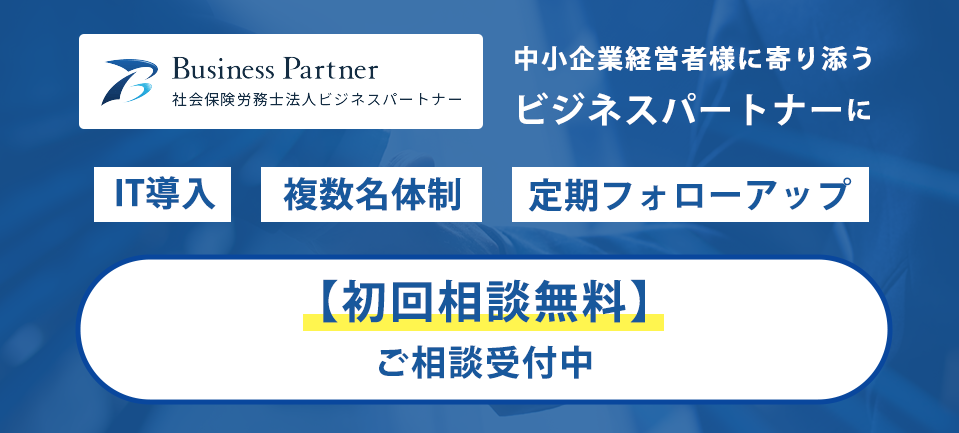「助成金を使えばコスト削減につながる」と耳にするものの、実際に申請しようとすると「どの制度を選べばいいのか分からない」「書類が多すぎて進まない」と感じている方も多いのではないでしょうか。助成金制度は企業にとって心強い支援策ですが、仕組みが複雑であるがゆえに、多くの企業が申請段階でつまずいてしまいます。
本記事では、助成金申請が「難しい」と感じられる理由を明らかにし、その壁を乗り越えるための具体的な解決策を、社労士の専門的な視点から解説します。申請成功のヒントを知り、確実に制度を活用できるようになるための内容をお届けします。
助成金申請が難しいと感じる3つの主な理由
書類が多く煩雑で時間がかかる
助成金の申請では、就業規則や労働条件通知書、出勤簿、賃金台帳など多くの書類が求められます。それぞれが制度ごとに異なる形式や記載内容を要求されるため、初めての企業にとっては非常に手間がかかります。特に、日頃から整備されていない労務書類があると、時間と工数が予想以上に膨らんでしまいます。
制度ごとの要件やルールがわかりにくい
助成金制度には数多くの種類があり、それぞれの目的・要件が異なります。例えば、「キャリアアップ助成金」と「両立支援助成金」では対象となる人材や取り組み内容がまったく異なります。また、同じ制度でも年度によって要件が変わることもあり、過去の情報を参考にすると誤って申請してしまうことも少なくありません。このような複雑さが、企業側の混乱を招いています。
労務管理体制が不十分だと不支給になる可能性がある
助成金は、制度の目的を満たしているだけでなく、日常の労務管理が適切に行われていることも求められます。たとえば、36協定の届出がなかったり、労働時間の管理が不十分だった場合、それだけで不支給となる可能性があります。書類が揃っていても、労務体制が整っていなければ助成金は受け取れません。申請の難しさは、こうした内部体制にも起因しています。
制度理解で変わる!助成金と補助金の違い
助成金と補助金の違いとは?
助成金と補助金はどちらも国や自治体からの支援制度ですが、性質や要件に明確な違いがあります。助成金は厚生労働省が所管し、主に雇用や労働環境の改善を目的としたものが多く、条件を満たせば基本的に審査なしで受給できるのが特徴です。一方、補助金は経済産業省などが所管し、審査や採択によって給付の可否が決まる「競争型」の制度であり、採択率が設定されている点に注意が必要です。
どちらも活用できるが目的が異なる
助成金は「人」に関する制度(雇用・育成・働き方改革など)、補助金は「モノや設備」に関する支援(機械導入・業務改善など)が中心です。つまり、採用や就業環境の整備を検討している企業には助成金、業務効率化や新規事業の立ち上げには補助金と、目的に応じた使い分けが必要です。この理解が浅いままだと、自社に合わない制度を選んでしまう原因になります。
制度ごとの申請先と担当省庁の違いに注意
助成金の申請先は主に労働局やハローワークですが、補助金は商工会議所や中小企業庁などが窓口になります。また、助成金は通年で申請可能なものが多いのに対し、補助金は公募期間が限定されていることが多く、タイミングを逃すと機会損失になりかねません。こうした行政の仕組みを正しく理解することで、申請の精度とスピードが大きく変わってきます。
つまずきやすい!申請実務で起こる5つの失敗例
スケジュール管理ミスで申請期限を逃す
助成金は申請のタイミングが厳格に定められており、事後申請ができない制度もあります。申請の準備に時間がかかるうえ、制度によっては雇用や取り組みの開始前に申請が必要なケースもあるため、制度を知ってから動き出すのでは遅すぎることもあります。
添付書類や記載ミスによる形式的な不備
提出書類に小さな不備があるだけで、申請が受理されないことがあります。就業規則や出勤簿、賃金台帳などは、内容が形式通りであり、かつ実態と一致している必要があります。記入漏れや捺印忘れ、数値の矛盾にも注意が必要です。
労務整備の不備で申請要件を満たせていない
制度上の要件を満たしていても、日常の労務管理が整っていなければ不支給になる可能性があります。たとえば、36協定が提出されていない、法定帳簿が未整備などの状態では申請が通りません。助成金は“帳面上”だけでなく“実態”が重視されます。
制度の選定ミスで自社に合わない申請をしてしまう
制度の目的を理解せずに申請すると、審査段階で弾かれてしまうことがあります。たとえば、キャリアアップ助成金では正社員化が条件ですが、契約内容が適合していないケースが後を絶ちません。事前に制度内容をよく確認することが重要です。
「やろうと思っていたけど…」と結局着手できない
助成金の存在を知っていても、「書類が多そう」「時間がない」と感じて先送りにする企業は少なくありません。そのまま制度の受付が終了し、機会損失となってしまうケースも多いのが現実です。
申請成功のカギ!今すぐできる5つの解決策
自社の状況に合った制度を選ぶ
助成金制度は多種多様で、自社の課題や取り組みに合ったものを選ぶことが第一歩です。制度ごとに対象者や条件が異なるため、目的や実施内容が合致しないと不支給になる可能性があります。厚生労働省や自治体の最新情報を確認し、自社の取り組みにマッチする制度を選定しましょう。
申請の全体スケジュールを逆算する
助成金申請は事前準備を含めると、1~2ヶ月以上かかることもあります。制度の受付開始日、実施時期、提出期限などを踏まえ、逆算してスケジュールを組むことが大切です。スケジュールを可視化しておくと、担当者間での抜け漏れも防ぎやすくなります。
労務体制(就業規則・勤怠管理)を見直す
助成金申請では、日々の労務管理の適正性が問われます。たとえば、36協定の提出や就業規則の整備、適正な勤怠記録の管理などができていないと、それだけで不支給となることもあります。助成金をきっかけに労務体制を再点検することも有効です。
過去の成功例を参考に事業計画を整備する
過去に助成金を活用した企業の事例や成功パターンを参考にすることで、事業計画や記載内容の精度が高まります。審査側に「制度の目的を正しく理解している」と伝える構成が重要です。各制度の事例集を参照するとヒントが得られます。
社労士など専門家のサポートを活用する
社内での対応が難しい場合は、社会保険労務士などの専門家に相談するのも一つの方法です。要件整理から書類作成、提出までの流れをトータルで支援してもらえるため、申請成功率も高まります。自社で抱え込みすぎないことが、失敗を防ぐポイントです。
申請はプロに任せるべき?社労士に依頼する3つのメリット
手続きの負担が減り、本業に集中できる
助成金の申請は、書類の準備から申請書の記入、提出先とのやり取りまで、非常に手間がかかります。とくに初めての申請では確認事項も多く、担当者の業務負荷が大きくなりがちです。社労士に依頼すれば、書類作成や提出の代行、手続きのアドバイスまで一括でサポートしてもらえるため、社内リソースを本業に集中させることができます。
最新制度への対応と適切な制度選定ができる
助成金制度は毎年のように見直され、名称や条件、受付期間が変更されることも珍しくありません。社労士はこうした制度改正にも精通しており、常に最新の情報をもとにアドバイスを提供できます。また、自社に合った制度の選定からスタートできるため、最初の段階でのミスマッチも避けやすくなります。
不支給リスクを減らし、成功率が高まる
申請の成否を分けるのは「制度理解」「要件把握」「書類の精度」です。社労士は過去の申請実績を多数持っており、どのような表現・構成で申請すれば審査を通過しやすいかを熟知しています。労務管理の視点からもチェックを行い、見落としやミスを事前に防げるため、不支給リスクを大幅に減らすことができます。
よくある質問(FAQ)に社労士が回答
Q1:助成金は誰でも申請できますか?
助成金は一定の条件を満たせば、法人・個人事業主を問わず申請可能です。ただし、制度ごとに対象となる業種や雇用形態、取り組み内容に違いがあるため、自社が該当するかをしっかり確認する必要があります。また、過去に労務違反や未届出の書類があると申請できない場合もあるため、労務管理の整備が前提となります。
Q2:顧問契約なしでも相談できますか?
はい、スポットでの相談や申請代行にも対応している社労士法人は多く存在します。特に「一度だけでも助成金を使ってみたい」「まずは制度の適用可否を知りたい」という企業にとって、スポット相談は有効な手段です。社会保険労務士法人ビジネスパートナーでも、無料相談や申請サポートをスポットで提供しています。
Q3:助成金と補助金は併用できますか?
多くの場合、助成金と補助金は併用が可能です。ただし、同じ事業に対して二重に給付を受ける「重複補助」は原則として認められていないため、それぞれの制度の対象範囲と使途を明確に分ける必要があります。計画段階で専門家に相談し、制度の組み合わせ方を設計することで、安全かつ効果的に活用できます。
まとめ|助成金申請の壁を越える第一歩は「相談」から
助成金申請が「難しい」と感じられるのは当然のことです。制度ごとに異なる要件、煩雑な書類、整備が求められる労務体制。どれも一朝一夕でクリアできるものではありません。しかし、正しい制度選びと事前準備、そして専門家のサポートがあれば、その壁は確実に乗り越えることができます。
本記事では、助成金申請において多くの企業が抱える疑問やつまずきやすいポイント、そして成功に導くための具体的な方法をご紹介しました。「やってみたいけど不安」「以前に失敗したから不信感がある」と感じていた方も、まずは小さな一歩を踏み出してみてください。
社会保険労務士法人ビジネスパートナーでは、制度の選定から申請代行、労務整備まで一貫してサポート可能です。スポット相談や無料診断も対応していますので、「この制度は使える?」「うちでも申請できる?」といった簡単な疑問からでもご相談ください。
助成金を活用することは、経営の安定化だけでなく、従業員の働きやすさや定着にもつながります。まずはプロに相談することが、確実な一歩となります。