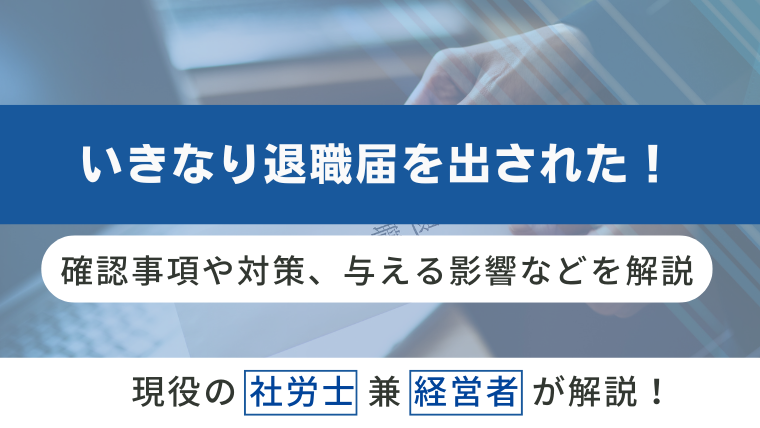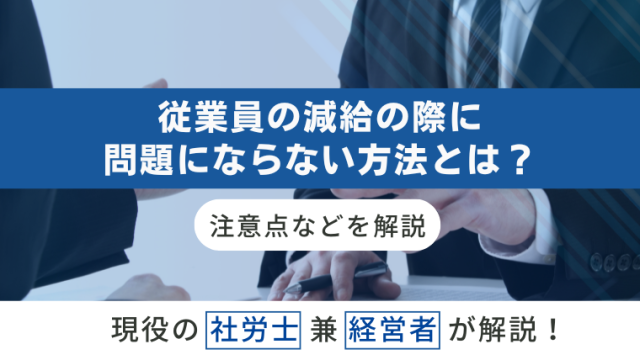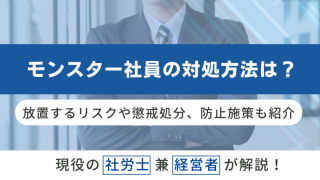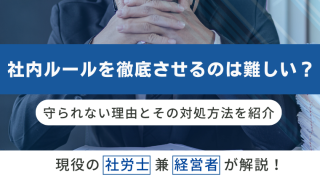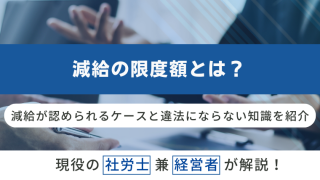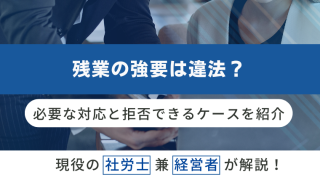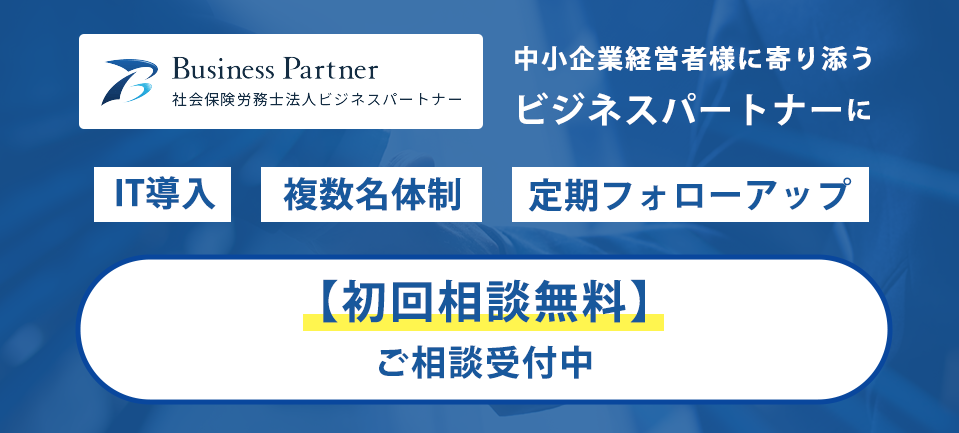ある日突然、従業員から「退職します」と書類を差し出され、対応に困った経験はありませんか?
-
引き継ぎが間に合わず、現場が混乱してしまう
-
退職希望日が急すぎて、引き止めもできない
-
退職理由が曖昧で、トラブルにつながるか不安
退職届の扱いには法的ルールと実務上の優先順位があります。本記事では、退職届を受け取った際に確認すべきポイントや、混乱を最小限に抑えるための具体的な対応策を解説します。
社会保険労務士法人ビジネスパートナー代表
結論:いきなり退職届を出されたら、基本的に受け入れるほかありません。
いきなり退職届を出された場合、国の法律的にも拒否することが難しいことがほとんどです。急に退職届を出された際には、受理をして、粛々と手続きを進めるほかありません。
ただ、ここで重要になるのは、今後そういった従業員を出さないために、再発の防止に努め、対策を練ることです。職場が従業員にとって居心地の良い場所としてあるために環境を整えることが重要です。
はじめに
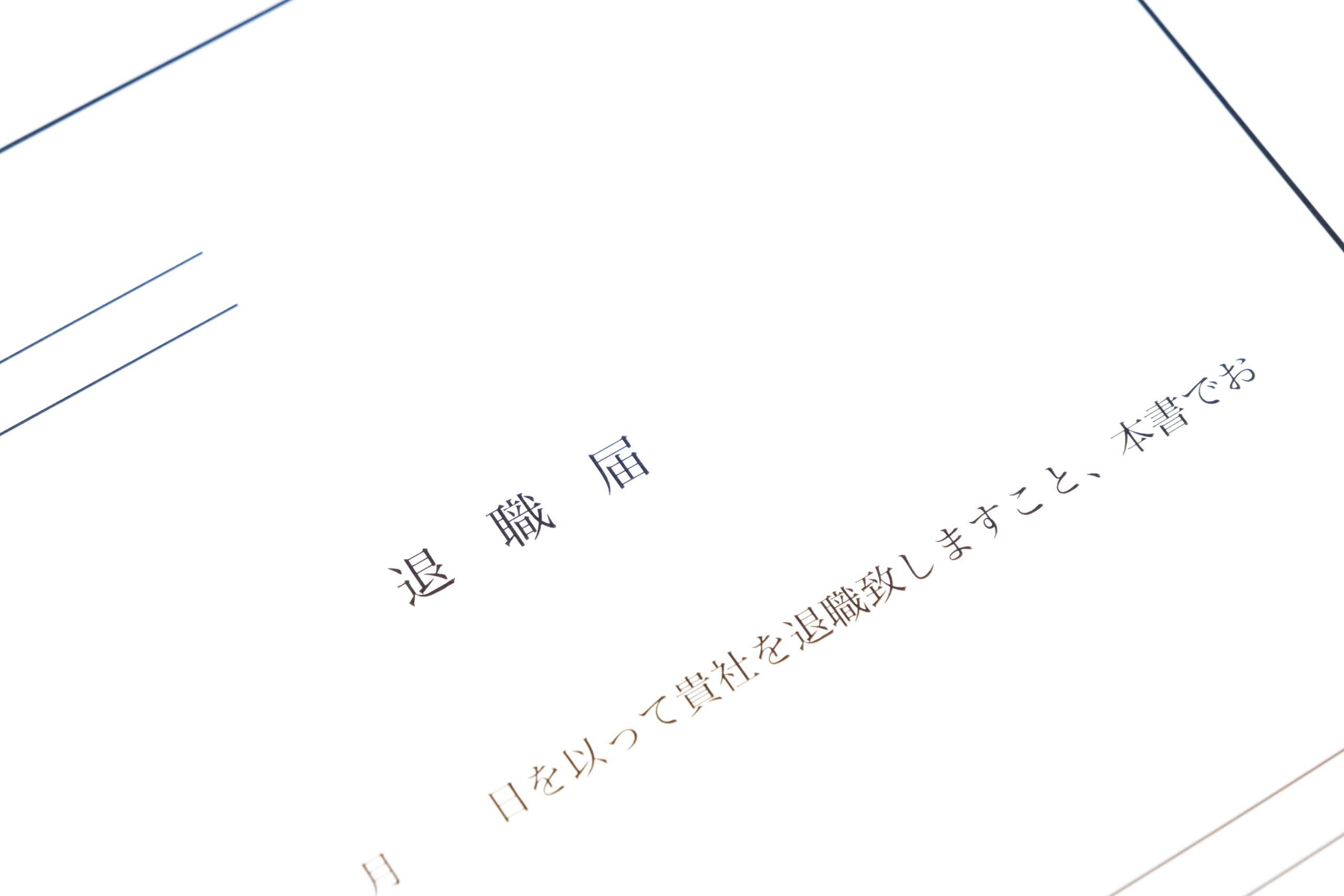
いきなり退職届を出されることは、特に中小企業には深刻な影響を与えます。
まずは業務の継続性が脅かされます。一人が複数の役割を担うことが多い中小企業では、その影響は大きいでしょう。
また、人材の補充も課題です。採用や育成には時間とコストがかかり、その間の負担は他の従業員に集中します。退職前に十分な引き継ぎができず、業務の質が低下する恐れも考えられます。
取引先や顧客の目から見ると、企業の安定性や信頼性に疑問が生じることがあり、これは中小企業にとって深刻な問題です。
いきなり退職届が出された際に企業に与える影響
ここからは、いきなり退職届が出された際に企業に与える影響を詳しく解説します。
業務への影響
突然の退職は、進行中のプロジェクトや日常業務に大きな支障をきたします。特に重要な役割を担っている従業員の場合、その影響は甚大です。納期の遅れや品質低下につながる可能性が高くなります。
また、退職した従業員の業務を他の従業員が引き受けざるを得なくなります。結果的に、残された従業員の負担が増大し、長期的には燃え尽き症候群のように従業員の心身に大きな影響を与えるリスクが高まります。
さらに、十分な引き継ぎ期間が確保できないため、業務の詳細が適切に伝達されず、残された従業員が混乱し、業務効率が大幅に低下する恐れもあるでしょう。
チームの士気への影響
突然の退職は、残された従業員のモチベーションを著しく低下させます。「なぜ辞めたのか」という不安や疑問が生じ、職場の雰囲気が悪化する可能性があります。
また一人の退職が他の従業員の退職を誘発する「ドミノ効果」が起こる可能性があります。これは組織の安定性を大きく揺るがす要因となりかねません。
さらに突然の別れは、チーム内の信頼関係を損なう恐れがあります。特にリーダー的存在が退職した場合、その影響は深刻です。
いきなり退職届を出された際の確認事項

いきなり退職届を出された際は、法的なルールや就業規則を確認し、適切な対応を心がけましょう。
法的なルール
労働基準法には、退職に関する具体的な規定がありません。しかし、民法では期間の定めのない雇用契約の場合、2週間前の予告で退職できると定められています。この点を押さえておきましょう。
また、従業員は退職の自由を有しており、会社側が無理に引き留めることはできません。ただし、就業規則に規定された予告期間を尊重してもらうことが望ましいでしょう。
それから、退職前の有給休暇取得希望には注意が必要です。原則として、退職日までの有給休暇を会社が拒むことはできません。しかし業務に著しい支障がある場合は、時季変更権を行使できる場合がありますが、強制的な行使は認められておらず、行使可能な場面は限られているといえるでしょう。
就業規則
自社の就業規則に記載された退職に関する規定を確認しましょう。予告期間や手続きの方法が定められていることが多いです。ただし、就業規則の規定が法律の基準を下回る場合は無効となります。
そのため、就業規則には、退職に関して明確に規定することが大事です。これにより、退職証明書や離職票の作成時に正確な記載が可能になります。
また、自然退職(突然の退職)事由として、契約期間の満了、休職期間の満了、行方不明・長期間の無断欠勤、在職中の死亡、役員就任、定年などを規定しておくことが望ましいです。
自社で就業規則を作成することもできますが、法律に沿った内容であることが重要です。また労働に関する法改正が行われた際は、就業規則の変更が必要です。トラブルを回避するためにも専門家に依頼する方が良いでしょう。就業規則作成・見直しの実績が豊富な当事務所にご相談ください。
退職届を受け取った後の流れ
退職届を受け取った際は、感情的な対応を避け、冷静に手順を踏むことが重要です。ここでは、退職対応から引き継ぎ・採用判断までの基本的な流れを整理します。
提出日・退職希望日・退職理由を確認し、本人の意思が明確かどうかをヒアリングします。
雇用形態や契約期間を確認し、退職予告期間や必要な手続きが遵守されているかをチェックします。
退職者の担当業務を洗い出し、優先順位を決定。適任者を選定し、マニュアル化や進捗確認を行います。
業務量や残業状況を踏まえて、正社員・契約社員・派遣社員など、必要に応じた採用を検討します。
退職届の控えや確認書を保管し、トラブル防止のために退職手続きを文書化しておきます。
退職届を受け取ったら、業務引き継ぎの指示や人材採用の検討が必要です。
まず、退職予定者の業務を洗い出しましょう。重要度と緊急度を考慮し、優先順位をつけます。次に、各業務を引き継ぐ適任者を選定します。経験や能力、現在の業務量を考慮して決定しましょう。
引き継ぎ方法もポイントであり、口頭での伝達だけでなく、マニュアルや手順書の作成を依頼すると良いでしょう。また、引き継ぎ期間中は定期的に進捗を確認し、必要に応じてサポートを行います。
業務の引き継ぎだけでは対応が難しい場合、新たな人材の採用を検討します。人材採用の判断をする際は、現在のリソース状況を確認することから始めてください。残業時間の増加や業務の遅延が見込まれる場合、採用は避けられないでしょう。
採用方法は、正従業員、契約従業員、派遣従業員など、状況に応じて選択してください。緊急性が高い場合は、派遣従業員の活用も有効です。長期的な視点では、正従業員の採用を検討しましょう。
いきなり退職届を出される事を防ぐための対策

いきなり退職届を提出されることを防ぐためには、企業側の積極的な取り組みが不可欠です。従業員の満足度を高め、働きやすい環境を整えることで、突然の退職リスクを軽減できます。
定期的な面談とフィードバック
従業員との定期的なコミュニケーションは、不満や問題の早期発見に役立ちます。
たとえば月に一度程度、上司と部下が1対1で話し合う機会を設けましょう。この面談では、業務の進捗状況だけでなく、キャリアプランや職場環境についても話し合ってみましょう。
定期的に従業員の声に耳を傾け、適切なフィードバックを行うことで、信頼関係が築けます。小さな不満が大きな問題に発展する前に対処できるでしょう。
柔軟な労働環境の提供
ワークライフバランスを重視する従業員が増えています。リモートワークやフレックスタイム制度の導入は、従業員のニーズに応える効果的な方法です。
たとえば、週1〜2日のリモートワークを許可したり、コアタイムを設定しつつ出退勤時間を柔軟にしたりすることで、従業員の満足度が向上します。ただし、制度の導入には公平性や生産性の確保に留意しましょう。
評価や待遇の見直し
公正な評価制度は、従業員のモチベーション維持に不可欠です。成果主義一辺倒ではなく、プロセスも重視した多面的な評価を心がけましょう。
また、評価結果を待遇に適切に反映させることも重要です。給与や昇進だけでなく、研修機会の提供や表彰制度の導入など、多様な報酬制度を検討してみましょう。
迅速に対応できるよう退職の対応ルールを作る

いきなりの退職に慌てないよう、あらかじめ対応フローを作成しておきましょう。たとえば、退職届の受理から業務の引き継ぎ、最終出勤日の設定まで、一連の流れを文書化することも有効です。
また、各部署の責任者や人事部門の役割を明確にし、スムーズな対応ができるよう準備します。その結果、混乱を最小限に抑え、残された従業員への影響も軽減されます。
社内異動の制度や研修制度を整える
キャリアアップの機会を提供することで、従業員の長期的な定着を促進できます。希望する部署への異動制度を設けたり、新しいスキルを習得できる研修プログラムを用意することも重要です。
また、外部講師を招いての研修や、オンライン学習プラットフォームの活用など、多様な学習機会を提供することで、従業員の成長意欲に応えられます。
従業員のキャリアアップや処遇改善に関して、助成金等を活用することも有効です。助成金に関する支援実績のある当事務所にまずはご相談ください。
厚生労働省の「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者(有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者等)の企業内でのキャリアアップを促進することを目的としています。非正規雇用労働者の正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
まとめ
いきなりの退職を防ぐには、適切な対応と予防策が大切です。また、法的ルールと就業規則の理解、迅速な業務引き継ぎ、そして人材採用の検討が重要です。
さらに、定期的な面談やフィードバック、柔軟な労働環境の提供、公正な評価制度の構築など、従業員との良好な関係づくりが突然の退職を防ぐポイントとなります。
これらの対策に不安がある場合は、社会保険労務士への相談も検討してみましょう。専門家のアドバイスは、法的リスクの回避や効果的な人事制度の構築に大きく役立ちます。従業員と企業にとって win-win な関係づくりが、安定した経営につながります。
当事務所では、無料相談やスポット業務にも対応しています。お気軽にご相談ください。