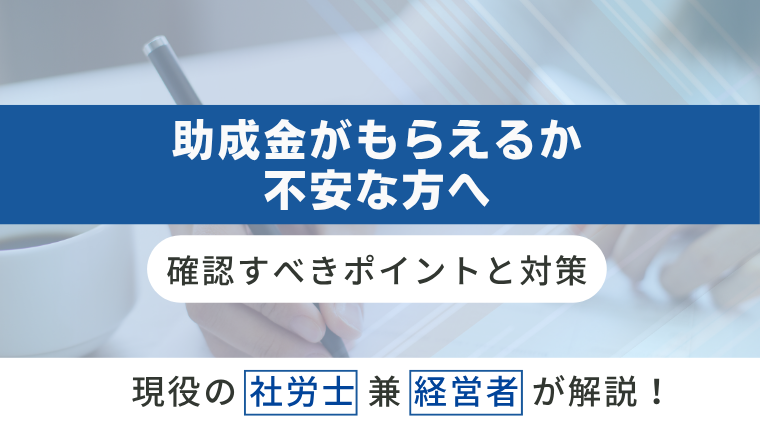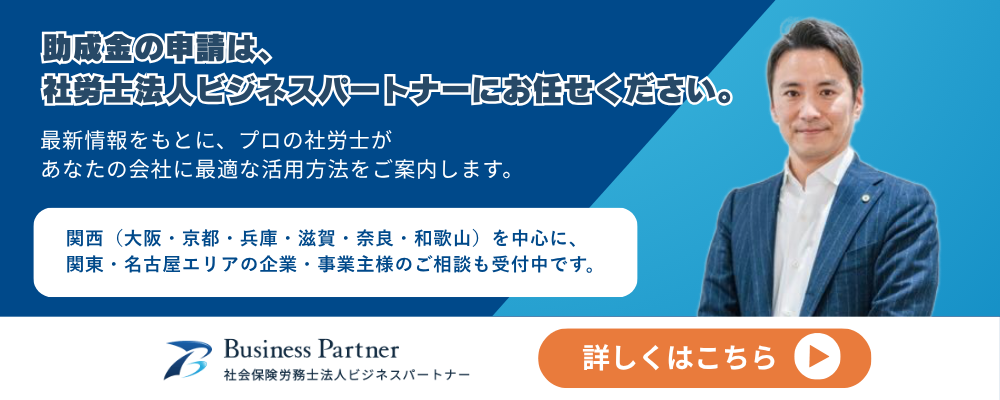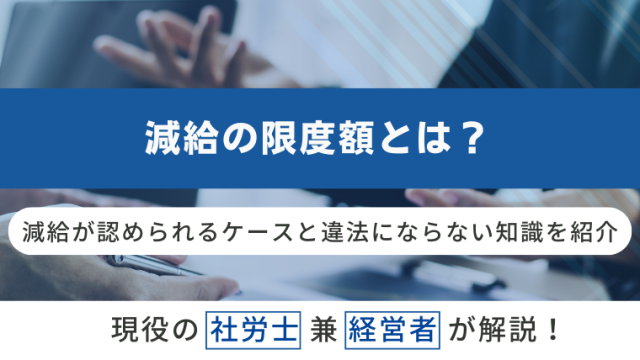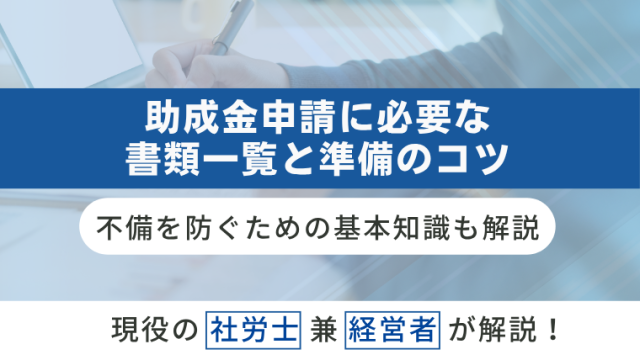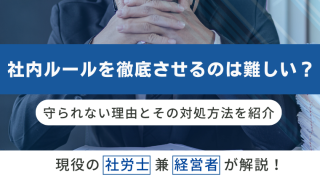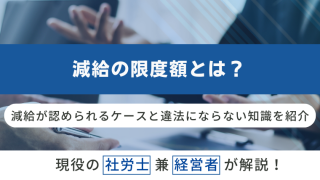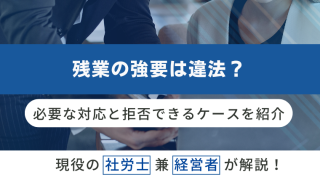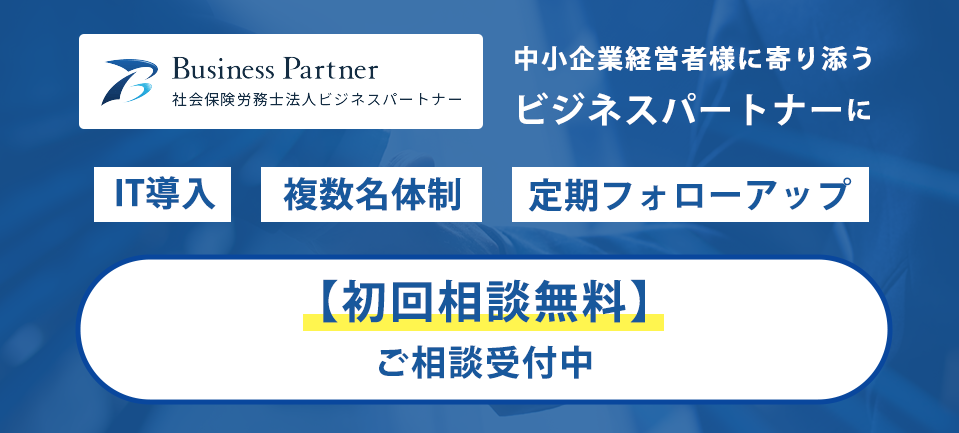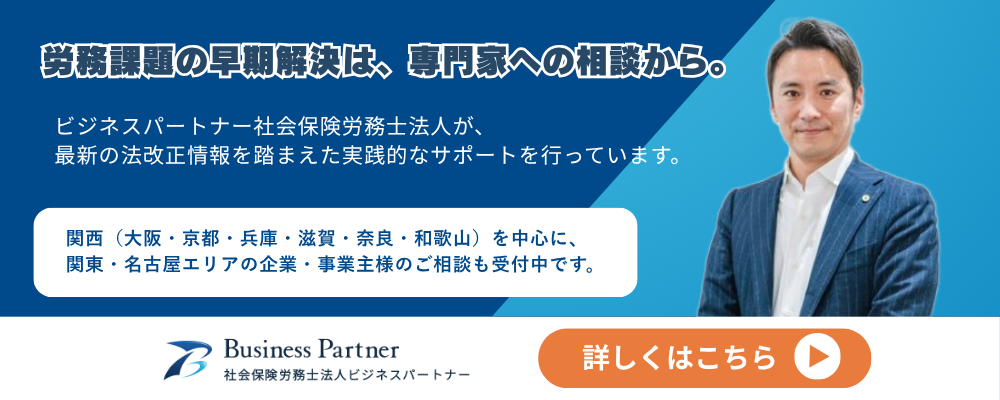助成金を申請したいけれど、「本当に自分の会社はもらえるのだろうか?」と不安に感じる方は多いのではないでしょうか。本記事では、助成金の受給可否に関するよくある不安の原因と、その確認ポイント・解消策をわかりやすく解説します。
\ 助成金について相談したい方へ /
\ お電話でのご相談もお気軽にどうぞ /
助成金がもらえないのでは?と不安になる理由

制度や条件が複雑で分かりづらい
助成金制度は種類が多く、それぞれで対象となる企業規模、雇用形態、支給対象の条件が異なります。そのため「どれが自分に当てはまるのか」が判断しにくく、不安につながります。特に中小企業や個人事業主にとっては、制度の全体像がつかみにくいことが申請をためらう要因になります。
情報が断片的で自社に当てはめにくい
検索エンジンやSNSで助成金について調べても、出てくる情報はバラバラで、何が本当に必要な情報か分かりづらいと感じる方が多くいます。
- 公的情報と民間メディアの情報が混在している
- 同じ制度でも年によって内容が変わっていることがある
- 成功事例と失敗例が混在し、判断に迷う
こうした情報の不確実性が、「うちは本当に対象なのか?」という不安を強めてしまうのです。
失敗経験や「もらえなかった」事例の影響
過去に助成金を申請して不支給となった経験がある企業や、周囲で「審査が厳しくてもらえなかった」という話を聞いたことがあると、再度の申請に消極的になりがちです。特に「理由がよく分からないまま落とされた」経験は、大きな心理的ハードルとなります。
専門用語や申請手順への心理的ハードル
助成金の申請には「雇用保険適用事業所番号」「計画届」「賃金台帳」など、普段使わない専門用語が頻出します。さらに、オンライン申請や書類提出の段取りも煩雑に感じやすく、次のような心理的負担を引き起こします。
- 自分でやるには難しそうと感じてしまう
- ミスしたら不支給になるのではという恐怖感
- 忙しい中で時間を割く余裕がない
こうした要素が「そもそも申請できるのか」という不安を膨らませているのです。
助成金を受けられない主な原因3つ
支給要件を満たしていない
最も多い不支給理由は「支給要件を満たしていなかった」ことです。助成金にはそれぞれ対象者や企業に課される条件があり、少しでも逸脱していると申請しても認められません。
- 雇用保険未加入
- 就業規則が未整備
- 雇用契約書の不備
- 過去に助成金不正受給歴がある
これらに該当していないか、事前にしっかり確認しておくことが必要です。
申請書類に不備・記入ミスがある
申請手続きでミスをすると、不支給や差し戻しのリスクが高まります。以下のような点がよく問題になります。
- 記載漏れ・記載ミス
- 提出期限に間に合わなかった
- 添付書類の形式が要件と異なっていた
これらは「やればもらえる」という誤解を招きやすいため、事前準備とチェックが重要です。
制度の目的と自社の状況が一致していない
たとえ形式上の要件を満たしていても、「制度の目的」と自社の取組内容が一致していなければ支給はされません。助成金には政策的な背景があり、それに沿った取組でなければ評価されません。
例として、「キャリアアップ助成金」は非正規雇用から正社員化を支援する制度ですが、単なる人員補充で正社員登用を行うだけでは対象とはなりません。非正規雇用から正社員化を行う際に、賃金や業務内容の改善、育成計画を伴う場合が対象になります。
受給対象かどうか確認する方法
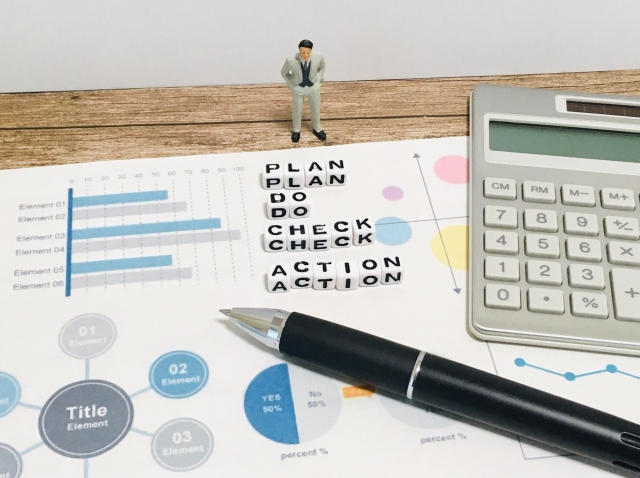
共通要件をチェックする(雇用保険・労務管理など)
助成金制度の多くには、共通して求められる基本的な支給要件があります。申請前に次のようなポイントを確認しておくと、対象かどうかを判断しやすくなります。
- 雇用保険の適用事業所になっているか
- 労働条件通知書・雇用契約書を適切に作成しているか
- 就業規則を整備し、労基署へ届出済みか
- 過去に不正受給などのペナルティがないか
こうした基本要件を満たしていない場合、制度の選定以前に申請資格自体がない可能性があります。
厚生労働省・ポータルサイトで制度を調べる
助成金がもらえるか不安な場合は、まず厚生労働省の公式サイトで公開されている「雇用関係助成金」一覧を確認しましょう。制度ごとに対象事業主や支給要件、提出書類が明記されており、自社の状況と照らし合わせるのに役立ちます。
また、「補助金ポータル」や「ミラサポplus」などのポータルサイトでも、キーワードや条件から該当する制度を検索できます。公的情報をもとに制度内容を把握することで、誤った認識やミスマッチ申請のリスクを減らせます。
調べる際は、制度名だけでなく最新の公募要項や注意事項まで目を通すことが大切です。
無料相談窓口や支援機関を活用する
助成金申請に不安がある場合は、各地域に設けられている無料相談窓口を活用するのもおすすめです。たとえば、ハローワークでは雇用関係助成金に関する相談に応じており、商工会議所や中小企業振興センターでも申請に関する支援を行っています。
また、地方自治体の起業・雇用支援窓口を利用すれば、制度の選定や必要な準備についてアドバイスを受けることも可能です。
こうした公的支援は初歩的な疑問にも対応してくれるため、社労士への依頼を検討する前の段階としても非常に有効です。
専門家(社労士)に初回相談して確認する
情報収集だけでは不安が残る場合、社会保険労務士などの専門家に相談するのが最も確実な方法です。助成金の実務に精通した専門家であれば、複数の制度の中から自社に合ったものを提案してくれます。
- 申請前の無料相談に対応している事務所も多い
- 書類整備から制度選定、実行支援まで一貫対応可能
- 自社の現状をヒアリングしたうえで判断してもらえる
特に初めての申請で不安が強い場合は、「もらえる可能性を高めるための第一歩」として、専門家の力を借りることをおすすめします。
助成金申請前にしておきたい対策
申請準備の流れを事前に把握しておく
助成金は「制度を知ったらすぐ申請できる」ものではありません。申請のタイミングや準備に必要な工程を把握せずに動くと、不支給や差し戻しの原因になります。主な準備事項は以下のとおりです。
- 対象制度の選定と申請要件の確認
- 支給申請前に必要な「計画届」の作成・提出
- 就業規則や雇用契約書の整備
- 支給対象期間中の実績報告に備えた記録体制の構築
こうした準備を事前に理解しておくことで、スムーズな申請につながり、不安の軽減にもなります。
まとめ:不安を放置せず、まずは「確認と相談」から始めよう
助成金が「もらえるか不安」と感じるのは、ごく自然なことです。制度の種類や条件が多岐にわたるなかで、自社が対象かどうかを判断するのは簡単ではありません。
しかし、支給要件の確認や公的情報の収集、専門家への相談といった基本的なステップを踏むことで、その不安は着実に解消できます。申請の失敗を恐れてチャンスを逃すよりも、まずは正しい情報と信頼できるサポートを得ることが大切です。不安を抱えたままにせず、一歩踏み出して「確認」と「相談」から始めてみましょう。